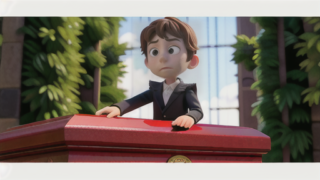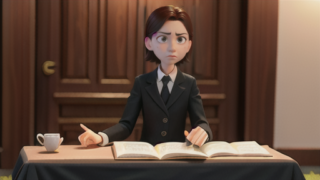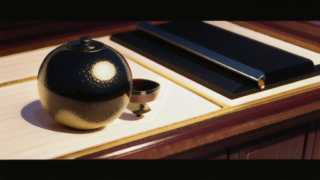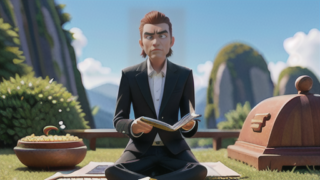お墓に関すること
お墓に関すること オルガン型墓石って? 近年人気の形の理由とは
オルガン型墓石とは、その名の通り、西洋の楽器であるオルガンを模したデザインの墓石です。近年、従来の和型墓石に代わる新しい形の墓石として人気を集めています。その特徴は、柔らかな曲線で構成された美しいフォルムにあります。従来の墓石にはない、優美で洗練された雰囲気が、故人を偲ぶ場にふさわしいとされています。また、オルガンは教会で用いられる楽器であることから、神聖さや荘厳さをイメージさせる点も、選択の理由の一つとなっているようです。