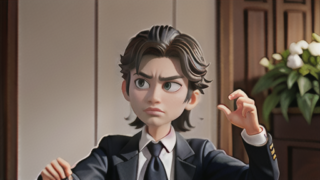お墓に関すること
お墓に関すること 墓石の定番「閃緑岩」ってどんな石?
閃緑岩は、火成岩の一種で、マグマが地下深くでゆっくりと冷えて固まった深成岩に分類されます。白や灰色、ピンク色などをした鉱物が、ごま塩のように散りばめられた見た目が特徴です。この鉱物の粒は、肉眼でも確認できる程度の大きさがあります。
日本では、墓石の材料としてよく使われていることから「御影石」とも呼ばれています。御影石の語源は、兵庫県神戸市の御影地区で産出される花崗岩の一種を指していました。しかし、現在では花崗岩と見た目が似ている閃緑岩も、御影石と呼ばれるようになっています。