 仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること 開眼供養とは? 仏像に魂を宿す儀式の意味と由来
開眼供養(かいげんくよう)とは、新しく造られた仏像や仏画に魂を迎え入れる儀式のことです。これは単なる飾り物ではなく、信仰の対象として魂が宿った尊いものとして開眼供養を通じて仏としてお祀りするために行われます。
 仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  お墓に関すること
お墓に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  お墓に関すること
お墓に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること 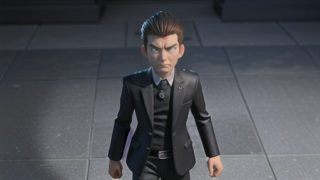 仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること 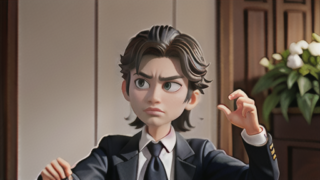 お墓に関すること
お墓に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること