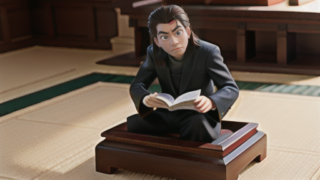お墓に関すること
お墓に関すること 永代供養とは?費用やメリット・デメリットをわかりやすく解説
- 永代供養の基礎知識意味や一般的な流れ
近年、お墓の継承者不足や、お墓の管理が難しいといった理由から、「永代供養」への関心が高まっています。
永代供養とは、簡単に言うと遺骨を寺院や霊園などに預け、その施設が永代に渡って供養と管理を行ってくれるシステムのことです。
従来のお墓のように、自分たちの子孫に管理を託す必要がないため、負担の少ない供養方法として注目されています。
-# 永代供養の一般的な流れ
永代供養は、一般的なお墓と比べて、比較的シンプルな流れで行われます。
具体的な流れは以下の通りです。
1. -永代供養を行う寺院や霊園を選ぶ-
費用や供養方法、施設の雰囲気などを比較検討し、自身に合った場所を選びましょう。
2. -契約手続きを行う-
費用や供養内容などを確認し、契約を結びます。
3. -納骨を行う-
遺骨を寺院や霊園に納めます。
4. -永代に渡る供養-
寺院や霊園が、永代に渡って供養と管理を行ってくれます。
永代供養は、生前に自身で契約することも、遺族が故人のために申し込むことも可能です。