 葬儀に関すること
葬儀に関すること 回し香炉とは?葬儀で知っておきたいマナー
回し香炉とは、葬儀や法要の際に参列者が順番に回し、焼香を行うための仏具です。香炉本体と、持ち手部分である「雲板」が組み合わさっており、雲板を回しながら香炉を隣の人へ渡していきます。一般的には、時計回りに回していくのがマナーとされています。
 葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること 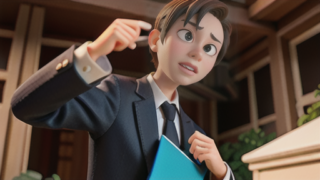 葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること