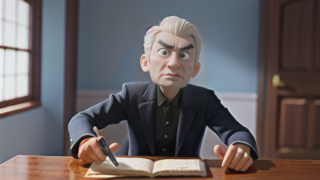葬儀に関すること
葬儀に関すること 意外と知らない?葬儀の「非信徒」の意味とマナー
近年では、宗教にとらわれない自由な形式で故人を見送る葬儀も増えてきました。しかし、依然として仏式やキリスト教式など、特定の宗教に基づいた形式で執り行われる葬儀も根強く残っています。
宗教色が強い葬儀に参列する際、「非信徒」という言葉を見聞きする機会があるかもしれません。「非信徒」とは、簡単に言えば「その葬儀で信仰されている宗教の信者ではない人」のことを指します。例えば、仏式の葬儀に参列するクリスチャンや、キリスト教式の葬儀に参列する仏教徒は、「非信徒」ということになります。
「非信徒だからといって、葬儀に参列できない」ということはありません。故人と親しかった人が、宗教の壁を超えて集い、共に故人を見送ることができる、それが葬儀の本来の姿だからです。しかし、非信徒として参列する際には、その宗教の作法やマナーを尊重し、失礼のないよう振る舞うことが大切です。