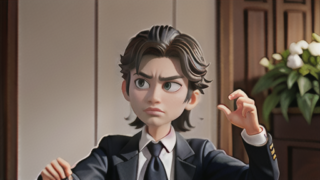葬儀に関すること
葬儀に関すること 「忌明」の意味と過ごし方とは?
「忌明(きみょう)」とは、故人の死を悼み、喪に服する期間である「忌中(きちゅう)」が明けることを意味します。一般的に、仏式の葬儀の場合、四十九日の法要である「忌明け法要(きあけほうよう)」をもって忌中が明け、忌明となります。
つまり、忌明とは、四十九日の忌明け法要後のことを指し、故人があの世から無事に成仏できたとされる期間を指します。この期間が過ぎると、喪服を着用せずに外出したり、友人との会食を再開したりするなど、日常生活に戻ることが許されるとされています。