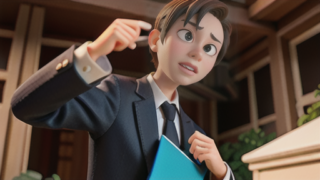お金に関係すること
お金に関係すること 香典のあれこれ:基礎知識とマナー
香典とは、仏式で行われる葬儀や法要の際に、故人を偲び、遺族に対しお悔やみの気持ちを表すために贈る金品のことで、主に現金を包みます。
香典は、かつて葬儀に必要な費用の一部として、香木や米などを霊前に供えていたことに由来します。時代とともに金品を贈る形へと変化しましたが、現在でも、葬儀にかかる費用を遺族と分担するという意味合いと、故人の冥福を祈る気持ちを表すという意味合いが込められています。
香典を渡す際には、表書きや金額など、いくつか注意すべきマナーがあります。次の章から、それらを詳しく解説してきましょう。