 葬儀に関すること
葬儀に関すること 神道の忌明け『清祓の儀』とは?
清祓の儀とは、神道において、死などの穢れに触れた場所や人を清めるために行われる儀式のことです。
人が亡くなると、神道ではそれを「穢れ」と捉え、一定期間、神様との通常の交流を控える期間を設けます。そして、この期間が過ぎた後、清祓の儀を行い、日常生活に戻ることを神様に報告し、再び神様との繋がりを回復します。
 葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  お墓に関すること
お墓に関すること  葬儀の準備について
葬儀の準備について  葬儀に関すること
葬儀に関すること  お墓に関すること
お墓に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  お金に関係すること
お金に関係すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  お金に関係すること
お金に関係すること  お墓に関すること
お墓に関すること  お墓に関すること
お墓に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  お墓に関すること
お墓に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  お墓に関すること
お墓に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  お墓に関すること
お墓に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  お金に関係すること
お金に関係すること  お墓に関すること
お墓に関すること  手続きに関して
手続きに関して 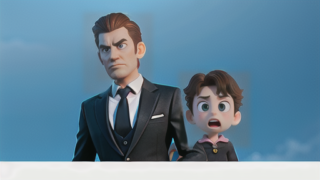 葬儀に関すること
葬儀に関すること  お墓に関すること
お墓に関すること