 葬儀に関すること
葬儀に関すること 葬儀の「釘打ち」:意味と現代における変化
「釘打ち」とは、葬儀の儀式の一つで、棺の蓋を閉じる際に、故人とこの世との別れを象徴する意味を込めて釘を打つ行為を指します。古くから日本各地で行われてきた伝統的な風習ですが、近年ではその意味合いも変化しつつあります。
 葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  お墓に関すること
お墓に関すること  お墓に関すること
お墓に関すること  お墓に関すること
お墓に関すること 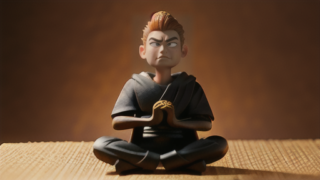 お墓に関すること
お墓に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  お墓に関すること
お墓に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  お墓に関すること
お墓に関すること  お墓に関すること
お墓に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  仏壇・仏具に関すること
仏壇・仏具に関すること  お墓に関すること
お墓に関すること