 お墓に関すること
お墓に関すること お墓の顔!外柵の種類と役割
お墓の印象を大きく左右する要素の一つに、外柵の存在があります。外柵とは、お墓の区画を囲む塀のことで、墓石と同様に、石材で作られるのが一般的です。
外柵は、単にお墓の範囲を示すだけでなく、外部からの侵入を防いだり、土砂の流出や雑草の繁茂を抑えるなど、重要な役割を担っています。また、墓石のデザインとの調和によって、お墓全体の雰囲気を大きく左右する要素の一つとも言えます。
 お墓に関すること
お墓に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  お墓に関すること
お墓に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  お墓に関すること
お墓に関すること  お墓に関すること
お墓に関すること  お金に関係すること
お金に関係すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  お金に関係すること
お金に関係すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  お金に関係すること
お金に関係すること  葬儀の準備について
葬儀の準備について  葬儀の準備について
葬儀の準備について  葬儀に関すること
葬儀に関すること  手続きに関して
手続きに関して  手続きに関して
手続きに関して  お金に関係すること
お金に関係すること  手続きに関して
手続きに関して  手続きに関して
手続きに関して  手続きに関して
手続きに関して  お金に関係すること
お金に関係すること  手続きに関して
手続きに関して 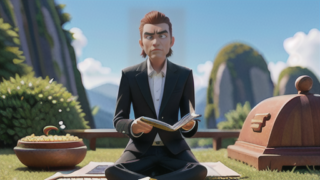 お墓に関すること
お墓に関すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること  寺院に関連すること
寺院に関連すること  葬儀に関すること
葬儀に関すること