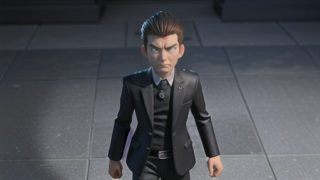葬儀に関すること
葬儀に関すること 海への最後の旅立ち:海散骨の基礎知識
近年、散骨という埋葬方法が注目を集めていますが、中でも特に人気を集めているのが「海への散骨」です。故人の遺灰を海へ還すこの方法は、従来のお墓とは異なる魅力とメリットを持っています。
海散骨とは、故人の遺骨をパウダー状にした遺灰を、海へ撒く埋葬方法です。古くから船乗りたちの間で行われてきたという歴史もあり、近年ではその自由なスタイルと自然回帰の思想から、多くの人々に選ばれています。
海散骨の魅力は、何と言っても壮大な海を墓標とするスケールの大きさにあります。また、場所の制約を受けないことも大きなメリットと言えるでしょう。故郷の海はもちろん、生前好きだった場所や思い出の海など、遺族の希望に沿って場所を選ぶことができます。
さらに、従来のお墓のように墓地の管理や費用の負担がないことも魅力の一つです。後世に負担をかけたくないという方や、簡素な方法を望む方に適した埋葬方法と言えるでしょう。